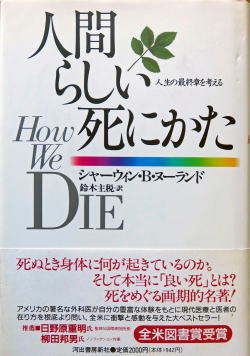3 看護の現場から
3-1 死より恐ろしいこと
内科病棟で働く経験7年目の「看護婦が見つめた人間が死ぬということ」から、宮子あずささんの体験を抜粋要約しました。人が死ぬ現場に立ち会った方ですから、赤裸々な姿を伝えていただけます。死ぬということがわかってきます。
死の問題は、そこに至る前に多くの人が経験する老いの問題を抜きにしては語れないと思うのです。そしておそらく、多くの人が最も避けて通りたいのが、この老いの問題でしょう。多くの人が、死そのもの以上に、老いて寝たきりになることを恐れています。
「もう80も越えているんだから、死ぬことはいいの。でも、寝たっきりになって人に迷惑をかけることを思うと、心配なのよ」「死ぬなら、ポックリ行きたいわ。願いはそれだけ」。多くの患者さんから、こんな声を毎日のように私たちは聞いています。
「脳卒中はね、ガンよりつらいのよ。この先何年、この状態が続くかと思えば、本人も家族も嫌になっちゃうよ。残された日々を悔いなく過ごそうとか、そんな張りもないんだ。先が見えているからこそ、人間は人に尽くせる。多少自分を犠牲にもできる。それがいつまでつづくのかわからないとなれば、嫌になっちゃうよ」
60代初めの若さで、脳梗塞のために人の手を借りないと生活できなくなったある患者さんはこういいました。彼の言い方は、ガンの患者さんの立場からすればなんてことを、となるかもしれません。でも、彼が言うような一面は確かにあると思うのです。
トップへ戻る
3-2 空手形は患者を苦しめる
長い老いを経て亡くなったある患者さんのお話です。彼女は83歳の、それは身体の大きなおばあさんでした。脳梗塞を何回か繰り返し、再発した梗塞でダメージを受けた脳の領域が大きく、右半身完全麻痺のため歩行困難になりました。
食事の量を減らして痩せるようにいわれていましたが、その過食が発作の遠因になっていたことは事実ですし、何よりその体重がリハビリの大きな障害になってしまったのです。車椅子に載せる看護婦ですら腰を痛めるほどですから、これから世話をする家族としては不安が募ったのもうなずけます。
「お母さん。そんなに食べないで、少しはやせてくれないとお世話できませんよ。私だって60なんですから」。娘さんはため息まじりに言っていましたが、寝たきりになった彼女にとっては、生きがいと言っては食べることだけ。
「まだ食べるの」と娘から言われながらも、娘の手を借りつつ一時間以上もかけて、食事をとるその姿には、すさまじい生への執念のようなものが感じられました。結局、彼女はこの娘に引き取ってはもらえず、老人病院への転院が決まりました。
転院を前に、娘さんも自宅へ引き取れないことに気が引けるのか、「リハビリが大切なんだから、リハビリの続けられる病院へ行きましょうね。それで歩けるようになったら引き取ってあげるからね」と、噛んで含めるように何度も言っていました。
高齢、肥満、右半身完全麻痺と悪い条件が重なった彼女が歩けるようになる可能性はほとんどなく、歩けるようになったらという仮定は彼女にとって、あまりのも遠いゴールだったのです。それでも彼女は、自宅に帰るために必死のリハビリをし、回復しない機能とくじけそうになる自分へのいら立ちばかりを募らせていったのです。
まもなく彼女は、すざましい抑鬱状態に陥ってしまいました。押し黙って返事もせず、ただ泣いているかと思うと、看護婦に対してものすごく攻撃的になったりします。娘さんはそんな母親に愛想をつかしたのか、面会にも来なくなってしまいました。
トップへ戻る
そんな彼女の姿を見ながら、私は、自宅に引き取れないなら引き取れないと、はっきり本人に言ってくれたらいいのに、と娘さんに対して軽い怒りを覚えました。いざ親が倒れたというときに、自宅で介護できないという家族が多いということ自体は、仕方がないことです。
ただ、患者さんは家に帰りたいと思い、家族は引き取れないとなれば、話しはそうそう八方円満というわけにはいきません。そこで引き取れない家族がきれいごとを並べれば、追いつめられるのは患者さんなのです。そうならないためには、むしろ対立を恐れずにきちんと話し合ってほしいのです。
私はこの娘さんに対して感じたのは、歩けるようになったらという空手形を出すことによって、「家に帰れないのはあなたが歩けるようにならないからよ」と責任転嫁するずるさでした。いくら彼女自身にも長年の非があるとしても、やはりこんな最後を見ていて彼女が気の毒でたまりません。
「脳卒中はね、ガンよりつらいんだよ」。そういったある患者さんの言葉を、私はその時しみじみと分かった気がしたものです。彼女は転院して間もなく、再発作を起こして亡くなったと聞きます。その時の彼女に子どもたちは、一体何と思ったのでしょう。
死ぬことそれ自体の悲しさ、切なさは同じでも、死に方には、やはり苦痛のすくない死と多い死があります。いじわるな見方をするなら、苦痛が長引けばどんな弱い面を見せないとも限らなかったでしょう。
死に際して人格が保たれるかどうかは、病気の成り行きにそのほとんどがかかっており、それを決めるのはただその人の運です。ですから、死に方を見てその人の生き方までを判断することは、死というものを甘く見ている気さえします。
どんなにいい生き方をしたとしても、その先にどんな死が待っているかなんて、誰にも分らないこと。人間は基本的に、降りかかってきた死を待つことしかできないのではないでしょうか。
トップへ戻る
3-3 ドラマチックな死
私が就職して間もなく、長年大学の名誉教授をされていた、80代後半の男性の死に立ち会いました。彼は、長い闘病の間も、人に対しては折り目正しく、配慮をなくされない人だったといいます。
私が就職したときにはすでにその病状は最終局面を迎えており、苦し気な息で時折り妻に何かを話す程度でした。それでも看護婦に対しては身体を拭いたり、身の回りのお世話をするたびに目をぎゅっとつぶって軽く頭を下げ、深い感謝の気持ちを示していました。
最後の時に、彼は家族を周りに呼び寄せ、一人一人ほんの一言ずつ短い言葉をかけたあと、「自分は、最後まで自分らしく逝きたいと思います」と目を閉じて言い、それが彼の最後の言葉になったのです。
家族も、医師も、看護婦も、その光景を前に、悲しみと同時に感動の涙を抑えることができませんでした。まだ看護婦としての経験の浅かった私にも、その彼の死をみて、立派な人はやっぱり立派に死んでいくものなんだなあと思いました。
その後も多くの人の死を見ていく中で、まず分かったことは、彼のように最後まで意識がはっきりしていて、きちんと何かを言い残して死ぬこと自体が、非常に稀だということ。ドラマの中に出てくる、ドラマチックな死にざまは、今の病院ではほとんどお目にかかれないと思って間違いありません。
トップへ戻る
3-4 元気な時の妻の姿を
苦痛が人格を変える。そのことを痛感させられたのは、ある70代の女性の闘病に出合った時でした。彼女は幼い時から足が不自由で、ようやく一人で歩ける状態だったのですが、持ち前の明るさと頑張りでそのハンディを克服し、幸福な家庭を築いていました。
肺がんで入退院を繰り返していたものの、最後の入院まで見た目には元気そのものでした。身体が弱っていてからも廊下の手すりにつかまりながら、一人で歩いている彼女の姿は、どこまでも前向きでした。私たちはよく、そんな彼女と軽口を叩き合ったものです。
「頑張って歩かれていますね」「ええ。みなさんのおかげで元気。みなさんの若さを分けていただいているようですよ。ほら、しわも少し伸びたでしょ」「今日も旦那様はご面会にいらっしゃるんですか」「ええ。ダーリンは私の顔を見ないと眠れないんですって」「それはそれは、ごちそうさま」「はいはい、お代はいりませんよ」
ところが運命はとても残酷。死を一気にひきよせることはせず、徐々に徐々に彼女を打ちのめしていったのです。絶え間ない吐き気で食事がとれなくなった彼女は、やがて歩けないほど衰弱してしまいました。吐き気止めの薬も、鎮痛剤もほとんど効果を示さず、彼女の衰弱は進むばかりでした。
初めは無理に笑顔をつくって「大丈夫ですよ。今が一番つらいときなんでしょうから」と自分を励ましていた彼女にも、だんだんと気力の限界が迫っていました。そしてある時、使った後のポータブルトイレを片付けるのが少し遅れたと言って、彼女は私たちに怒りを露にしました。
「全く、今の若い子は何も気がきかないんだから」。その時を境に、私たちの蜜月は終わりを告げたのです。それ以来、彼女は誰にも心を開かなくなりました。看護婦に対していつもにこやかに接していた彼女からは創造もできない沈黙と冷笑が、すべての援助に対しての答えでした。
体を拭いても、便器で排泄の世話をしても、食事の前に手を洗うようお湯を汲んで持って行っても。彼女はただ硬い表情で「どうも」というだけで、私たちと何も話そうとはしてくれません。しだいに私たちも、彼女に対して当たらず触らずのかかわりになっていきました。
もちろん私たちも、体の具合が悪くなったら、誰だっていい機嫌で人には向き合えません。しかし、元がいい人だっただけに、その変化の激しさは、ベテランの看護婦をも戸惑わせたものでした。それから家族すら耐えがたかったようで、見舞いの足が遠のいてしまい、そのことがまた、彼女のいらだちを誘っていたように見えます。
結局彼女は、すべての人と気まずいままに亡くなってしまいました。後に残ったのは何とも言えない無力感。もう少し苦痛を取ってあげられたなら、彼女の人格はあそこまで倒壊せず、家族と共に思い出深い何週間をつくってあげられたにのではないか、という後悔もありました。
「元気な時の妻のことを覚えていてください」。夫は、私たちにそう言い残して、妻の遺体とともに自宅へと帰っていきました。
トップへ戻る
3-5 シスターの死
信仰は死への恐れを癒すすか。これは就職した当初から私が抱いている疑問です。しかし、お坊さんやシスターといった、宗教においては人を教え導く側の人であっても、心穏やかに人生の終わりを迎えるとは限らないことを知ったのです。
シスターは80代全般の女性で、ごく若い時期から修道院の中で生活をはじめ、その修道院ではトップの位置におられる方でした。二年前から治療で何とか抑えていた肺ガンがいよいよ悪くなり、今回は最後の時を過ごすための入院だったのです。
つい最近までは修道院の中を歩き回り、軽い仕事もこなしていたといいます。しかし、入院時にはそのきびきびした面影はなく、ぐったりと寝たきりで言葉も切れ切れでした。その日から私たち看護婦は、嵐のように鳴らしまくるナースコールに泣かされることになります。
「ちょっと枕を高くしてちょうだい」「ちょっとお水を飲ませてちょうだい。そんなぬるいのはダメ。氷を一杯入れて」「ちょっと、暑いから毛布を取ってちょうだい」「ちょっと、おしぼりで顔を拭いてちょうだい」。たしかに、これらの頼みはどれも、もっともと言えばもっとなものばかり。
身をよじるのもしんどい彼女にとっては、無理のないことだったかもしれません。そのこと自体は仕方がないこととわかりつつも、私たちがどうにもつらかったのは、彼女の言い方でした。「ちょっと、〇〇〇をして」というときのその言い方は、まるで召使への命令そのもの。
そして、最後にわたしたちが受ける言葉は「どうも」でもなければ「ありがとう」でもありません。「よし」という、お許しの言葉にほかならなかったのです。中でも、忘れられないのは「カーテン事件」。主治医が看護婦とともに彼女のもとを訪れたある朝、少し開いた窓から風が入って、カーテンがかすかに揺れていたのです。
それを見て彼女は「ちょっと、カーテンが揺れないように」と言います。それで看護婦が窓を閉めると「ちょっと、窓は閉めないように」という。どうしたらよか戸惑う看護婦を横目でちらっと見た彼女は、とどめにこう言っそうです。「ちょっと、頭を使って」。
トップへ戻る
言われた看護婦のほうは怒りを抑えながらも、カーテンを窓に絆創膏で張り付けたそうです。いかに末期の患者とはいえ、あまりと言えばあまりの言いよう、それも無表情な抑揚のない言葉で言われ分、胸にグサッと刺さるのです。
彼女は話すことが大義になり、面会に来る部下に頼んで、部屋中に頼みごとのメモを張らせたのです。「大きな声を出せませんから、口元に耳を寄せてください」「病院の岡座は好まないので、おかゆに冷蔵庫の粒ウニをに押せてください」
「急いで食べられないので、ゆっくりご飯を一口ずつ食べさせてください」「手元にかならず水をおいてください。容器が重いと困るので、半分だけ入れること」「他にもお願いしたいことがあるかもしれないので、部屋を出るときは必ず他に要件がないか確認してから出て行ってください」
これらの頼み事はみな、短冊のようなメモ用紙に書かれ、ベッド棚や壁などにテープで貼られています。私たちが入っていくと、彼女は「言わずとも分かれ」とばかりに視線で目を見やり、実際ほとんど口をきこうとしません。
そしてある時、彼女が顎をしゃくって用を言いつけたときに、ついに私の堪忍袋の緒が切れました。きちんと口元に耳元へ近づけて言うことを聞き取ろうとしていたのに。私は無性に悔しくなりました。とはいっても、相手は病人ですから、やはり言いたいことを言い返せません。
正直言って、怒りを通り越してあきれたという気持ちもありました。私は反射的にこう彼女に尋ねていました。「神様はあなたを力づけてくれているのでしょうか」と。この問いに対して、彼女はこういったのです。「神様は、私が死を前にして気弱になって、どんな醜いおのれをさらそうともわたしを許し、天国に迎え入れてくれるのです」
その瞬間、私は何とも言えないむなしさを感じました。これまでの過程がどうであれ、彼女の信仰の帰結は、やはり「自分さえよければ」の利己主義だった気がしてなりません。結局彼女は、誰にも看取られずに亡くなりました。亡骸は遺言通り、純白のシスターの衣装に包まれました。
トップへ戻る
3-6 老衰という死
私が見た「ああ、これが老衰なんだなあ」と思える亡くなり方をした患者さんは、94歳の女性でした。食事がとれないことによる衰弱で、何回か入退院を繰り返した彼女の最後の入院は、約一か月。その経過を見ながら、私は人老いて死ぬというのはこういうことなんだなと不思議な感動を覚えたものです。
入院してきた時には、仏様のような顔でにこにこ笑い、聞きとれない声で何かぶつぶつと呟いていた彼女。ところが、三日目になって突然意識がなくなったのです。血圧や呼吸は正常。でも、名前を呼んでも、揺さぶっても、彼女は決して目覚めません。
すぐに個室へ移された彼女を家族がかわるがわる手を取り、来るべき時に備える体制になったのです。「おかあさん」と娘が呼んでも返事はない。「おばあちゃん」孫が読んでも返事はない。ところが、意識がなくなって4目の朝、彼女は突然目を開け、来た時と同じように穏やかなほほえみを浮かべたのです。
そしてまた、聞き取れない声で、ぶつぶつ楽しそうに何かを言い始めました。さらに3日たつと、また彼女は意識がなくなったのです。私は、彼女の意識の回復は、人が亡くなる前にありがちな、一時の小康だったのかと思い、ぬか喜びした家族を気の毒に思いました。
「お母さん」「おばあちゃん」そしてまた同じことが繰り返されます。しかし4日たつと彼女は目覚めました。3日目覚めて3日眠る。ここにきて私たちは、それが彼女の睡眠パターンなのだとわかったのです。
家族も、その人体の神秘に驚いていました。(医学的根拠はありません)一か月も経つ頃、この生理パターンははっきりしなくなり、少しずつ鈍くなっていきました。点滴を刺そうにも、枯れた身体には血管すら浮いてきません。
家族も積極的な治療を望んでいませんでした。「もうずいぶんな年ですから、痛いことは止めていただきたいと思います」。いつもついている娘が、申し訳なさそうに言いました。なにもしないことが実は私たちにとって難しいことなのです。少しずつ呼吸が浅くなり脈が弱くなっていきました。
「おばあちゃん、わかる」遠くの親戚もかけつけ、親族一同が介して和やかな中に、残り少ない日々が過ぎていきます。彼女はますます穏やかな顔になり、本当に仏さまにどんどん近づいていくようでした。夜は娘が一人付き添い、巡視に回るたびに私たちに声を掛けます。
トップへ戻る
「全然苦しんでいないんですね。母がわりと最近まで元気だったから気かつかなかったけれど、わたしも75のおばあちゃんなんですよね。平均寿命からいけば、母なんて本当に長生きなほう。私がこの年まで生きられるかどうかなんて、わかりません。
母をみとったらすぐに、今度は私が追いかけるかもしれない。そう思うと、お母さん、あなたは苦しまなくってうらやましいわ。わたしを呼ぶときはどうやって連れて行ってくれるのって、話しかけているんですよ」。言われてみれば、まさにその通りなんですよね。
「わたしも楽に死にたいわ。母みたいに、だんだん眠ってる時間が長くなっていって、いいなあ、お母さんは」。彼女は駄々をこねるように言います。その時の彼女の顔は、いくつになっても娘の表情でした。長い眠りからついに彼女が目覚めて亡くなったのは真夜中のこと。
看護婦が部屋を訪れると、彼女の呼吸は永遠に止まっていました。傍らで、娘はベッドに顔を伏せて眠っていました。その知らせたとき、娘がどんなに悲しむかどきどきしながら娘を起こしたそうです。母親の突然の死を聞いた娘は、眠そうに眼をこすって、ちょと身体をぴくっと震わせてから静かに言いました。
「ああ、最後まで苦しまずに亡くなったんですね。うらやましい」。彼女の気持ちは、母の死を越えて、いつか来るであろう自分の死に、どうしようもなくいってしまうのでしょう。
改めて言うのもおかしいのですが、人の死というものは、いつでも悲しいものです。いくら年を重ねたと、いわゆる大往生と誰しもが納得する死であっても、全く涙のない死というものは、ほとんどありません。
患者さんを見送っているうちに、最近私の中に新しいい死する対する感覚が生まれてきています。信仰を持たない私が一言でいえば「死とは、だれもがいつか行くところへ、先に行くことなんじゃないか」という感覚です。
お年寄りの亡くなり方を見ていると、死ぬっていうのは植物が枯れていくのといっしょなんだなあと、よくわかります。食べられなくなり、水分が取れないと、人間もやっぱり乾いていく。そこに無理に点滴を入れてよみがえればいいのですが、そうでなかったらむくんで、時には悲惨な状態になってしまう。
亡くなり方がきれいにという意味では、点滴は少なめに、自然に枯れるにまかせたほうがきれい。もちろん元の病気によっては治療の都合上そういかないこともありますが、可能な限り余分な水分を入れないほうがいいと、いつも思っています。死は、自然に枯れていくことなのです。
トップへ戻る
参考資料:人間らしい死に方(シャーウイン・B・スーランド、河出書房新社)、看護婦が見つめた人間が死ぬということ(宮子あずさ、海竜社)、ヒューマニエンス死の迎え方(NHK)、肥満症診察ガイドライン・日本人の食事摂取基準(厚生労働省)など。